こんにちは、しなぴーです★
最近では就活を控えた看護学生さんからの相談メールも多く寄せられます。
ということで今日は、そんな看護師の卵さんのお悩みに私なりの考えをお話していきたいと思います(*^-^*)
初めての就職先はどうやって決めた?
看護師となって初めて働く場所って重要な気がしますよね。
私もそう思います。
でもみんなどうやって就職先を決めてるんだろうって疑問に思いませんか?
どうやって就職先を選んだか?
まずは病院選び
- 前から決めていた憧れの科がある病院へ就職
- 学生時代のアルバイト先へそのまま就職
- 奨学金を受けた病院へ就職(お礼奉公)
- 教育体制がきちんとしている病院へ就職
- お給料と病院の規模をみて就職
- 就職活動が遅れ締め切りが間に合った病院へ就職
最後の⑥の学生っておバカな子だなー。そう思いましたよね?
これ実は私なんです。
進路とか就職とかゆー将来の事を決めるのがとっても下手で、ついつい考えるのを後回しになってしまう傾向にある私。
なので、私は締め切りが間に合う病院の中からお給料や規模を見比べて就職先を決めました。

だから、早い段階から自分の将来について考えてる人を見るとそれだけで「偉いな~!ちゃんとしてるな~!」と感心してしまいます。
話を戻します。
前から決めていた憧れの科がある病院へ就職
このパターンで就職する人は結構多いと思います。
夢が目標はしっかりと定まっていて、そこに向かってまっしぐらー!って感じで一番優秀なイメージありますよね。
やっぱり目指す先がハッキリしてるってブレない!強い!時間を無駄にしない!って感じがして憧れます。
学生時代のアルバイト先へそのまま就職
これも実は多いです。
看護学校の種類によっては、病院で働きながら学ぶというスタイルもとれます。
『バイト先の病院が居心地良いからこのまま就職しよう』ってなるみたいです。
その病院が自分に合っていると感じるから就職しようと思ったんでしょうし、これって一番スムーズな形でストレスが少なそうですよね。
奨学金を受けた病院へ就職(お礼奉公)
『看護学校の学費を出すから免許取ったらウチで〇年は働いてね~』っていう契約のことをお礼奉公と言います。
お礼奉公にも色んなものがあって、都道府県の奨学金の場合は『学費出すから〇年はここ(都道府県内)で働いてね~』ってゆーのもあるみたいです。
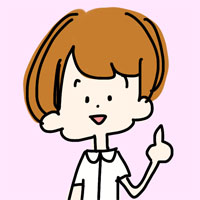
学費を出してもらえるのってありがたいし、既定の年数その病院に勤めれば返済も必要なくなるようです。
私のクラスメイトにも何名かいましたし、このシステムで就職した子は堅実で先を見据える力があるなーと思いました。
だって、お金はかからないし就職先も確約されてるんですから(*^-^*)
教育体制がきちんとしている病院へ就職
就職先の教育体制てかなり重要ですよね。
きちんと教えてくれる体制があってこそ安心して業務に取り組めるし、仕事を覚えられる。
でも、求人情報に記載されている文面だけじゃ「本当に教育体制が整っているのか?」は分からないので、その点だけは要注意です。
お給料と病院の規模をみて就職
これも大事ですよね。
例えば、色んな分野の看護を学びたいと思っている人が小さな町の個人病院に就職しても、学べる分野は狭いですよね?
逆に、じっくり人と関わりたいとか一つの科を極めたいって人にとって、大病院のような異動を繰り返しながら働く場はなんとなく違うなってなりますよね。
それに、人それぞれの環境に見合った生活費を得ることが出来るかどうかも、生きていく上では重要な条件となります。
配属科の希望はどうやって決めるの?
〈病院選び〉と〈配属科選び〉については、前後する場合があります。
『この科があるからこの病院に決めた』っていう人も多いです。
しかし『看護師になりたいけど特定の科を目指しているわけではない』ってゆー若かりし頃の私みたいな考えの人も沢山います。
その場合は大抵急性期を勧められます。
なぜ急生期をすすめられるのか?
それはきっと、患者さんが運ばれてくる⇒手術や濃厚な治療をする⇒術後の経過観察。という感じで患者さんや疾患を流れで見ることが出来る場だからだと思います。(あと、必要とされる看護技術も慢性期に比べると多いから。)
『新卒は沢山のことを吸収するタイミングだから、患者さんや疾患を流れで見て把握できるようになってほしい』という教育者の希望も大いに関係あると思います。
私も恩師には『とりあえず急性期希望したら?』と言われましたし。
みんな急性期を目指した方が良い?
個人的な考えを申しますとNOです。
だって、慢性期でも学べることは沢山ありますもん。
急性期と慢性期では患者さんの状態が違うため看護の内容が違ったりするので、病棟のスケジュールの組み方や時間の流れ方に違いがあると思います。
そこそこで学べることが違うでしょうが、急性期の患者さんは経過と共に慢性期に移行しますし、慢性期の患者さんが急変することもあります。
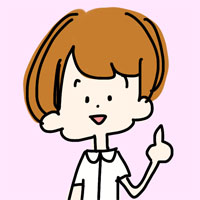
確かに指導する側には、『早い段階で沢山のことを経験してほしい』っていう思いがあると思います。
例えば、看護師2年目になった時『これまで医療処置がほとんどない病棟にいたのにいきなりICUに異動!?』なんてことになったら、そのナースを絶望に追い込んでしまうかもしれませんからね((+_+))
だから、まずは急性期で色々経験して、ゆくゆくはやりたい看護を出来る科へ。っていうスタイルが理想とされるスタイルになったのかなーと思います。
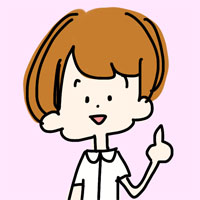
急性期急性期って一括りにしてますけど急性期にもいろいろあって、整形外科だって急性期だし脳外科だって急性期だし、精神科の急性期だってありますしね。
自分で色々経験して初めて合う合わないを知れると思いますし、職場や同僚によっても居心地とか働きやすさって変わってきますしね。
しなぴーは慢性期スタートだった
かくゆう私は、どっぷり慢性期からのスタートでした。
採用試験の際、面接で『希望する配属科はありますか?』と聞かれ、多くの学生が『急性期を希望します!』と答える中、私は「患者さんとじっくり関わりたいので慢性期を希望します!」と答えました。
新卒のしなぴーはなぜ慢性期を希望したのか?それは・・・
急性期が怖かったから!( ノД`;)
これに尽きます。
ビビリで心配性な私は「毎日緊迫しているであろう急性期ではとてもじゃないけど働けない!」と決めつけていました。
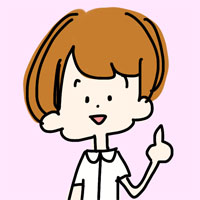
慢性期配属後のしなぴーは、急性期に配属された同期の学びのスピードに面喰ったりもしました。
かと思えば、同じ慢性期病棟のデキル同期と自分を比べ落ち込んだりもしました。
自分だけが出来が悪いと思い込んじゃうんです、新人の頃は特に。
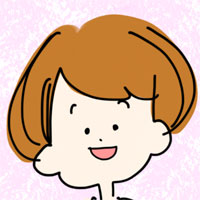
それでもやっぱり同期って貴重な存在なんですよ。
良いライバルだと思って切磋琢磨したり、目標にしたり。
病棟は違えど、同期の存在は大きかった!
看護師1年目を乗り切るためには重要な支えだったことは確かです★
まとめ
慢性期には慢性期の良さ、急性期には急性期の良さがあるんです。
たまに、『急性期に比べたら慢性期は楽そうだよね~』なんて言ってる人を見かけます。
現場が違えばその現場なりの難しさや忙しさがあるし、日々変わる患者さんの状況次第で大変さは変わってくるものなのに。
それを分かろうともしないで慢性期を下に見るようなこと言ってる人を見かけたら
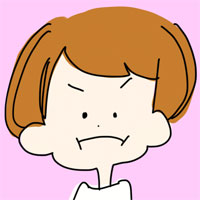
と呆れてしまします。また話がそれてしまいました(-_-;)
結局何が言いたいかというと、やりたいことがハッキリしている人はそこに向かって突き進めばいいし、ハッキリしてなくてもなんとかなる!私みたいに♩ってことです。
どうしても【希望する配属科】を決めなければならないのならば、興味がある分野をいくつか挙げるのも手かと思います。
また、「私は○○に興味があって、○○みたいな看護師になりたいんだけど、そうなるには何科を選べば良いんだろう?」と自問自答するもよし、学校の先生や家族や仲間に尋ねてみるもよしです★
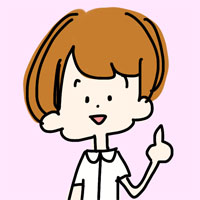
誰のものでもない、あなたの人生ですから♩
今回も長くなってしまいましたね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます★



